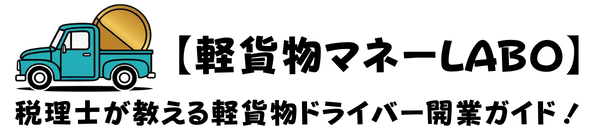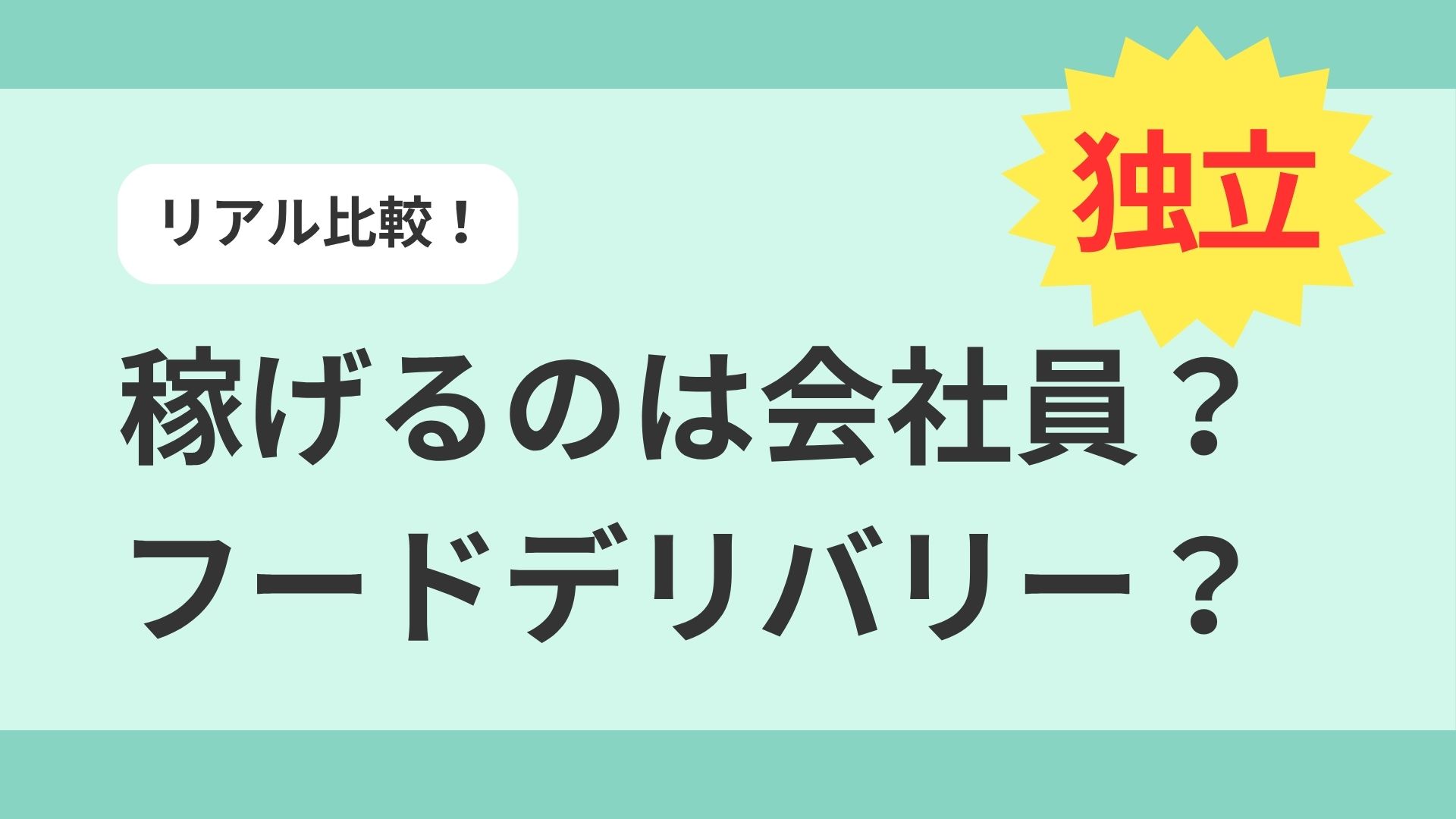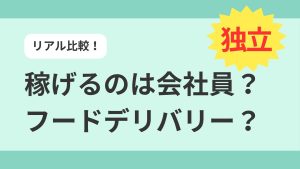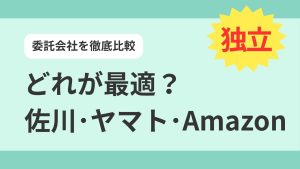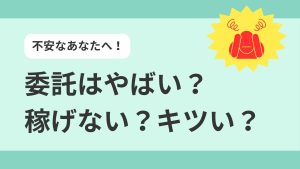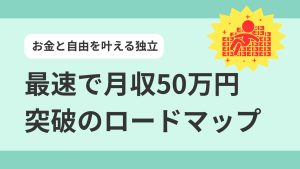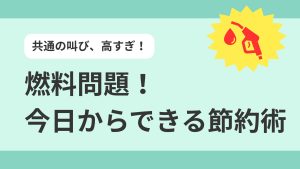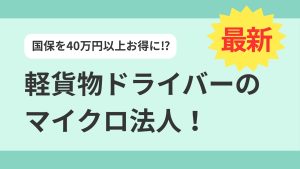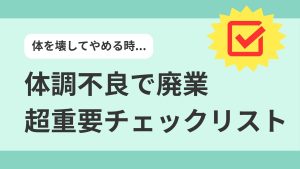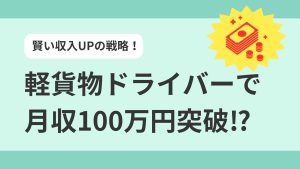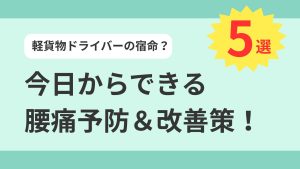「スキマ時間を活用したいな」
「自分のペースで働きたいな」
「頑張った分だけ稼ぎたいな」
そう考えて、フードデリバリーのお仕事に興味を持っているあなた!この働き方は、自分の都合に合わせて自由に働ける魅力的な選択肢ですよね。そして、有名なプラットフォームといえば、やっぱり**「Uber Eats(ウーバーイーツ)」と「出前館(でまえかん)」**でしょう。
もし、あなたが「フードデリバリーって、稼いだら全部自分のものになるんでしょ?」と考えているとしたら、それは少し現実と違います。どんな働き方でも、「額面」や「売上」といった、表面的な金額が、そのまま全部「手取り」として自由に使えるわけではないからです。
実は、Uber Eatsと出前館を上手に組み合わせて仕事をしている私の友人(ベテラン勢!)から、**「年間で売上(経費を引く前)が450万円~500万円ぐらいになるよ!」**というリアルな話を聞きました。これだけ聞くと、「おお!すごい!稼げる仕事なんだ!」って思いますよね。
でも、その友人は**「でも、経費も年間で150万円ぐらいはかかるかな」**とも言っていました。「え?経費ってそんなにかかるの?」って、ちょっと驚かれるかもしれません。
さらに、これはフードデリバリーに限った話ではなく、会社員として働いている方も、給料から自動的に差し引かれているものがありますし、仕事にかかる自分持ちの費用もあります。
今回のブログでは、これからフードデリバリーを始めてみようと思っているあなたに向けて、**「Uber Eatsと出前館を両方使うと、実際どうなるのか?」「どれくらい稼げる可能性があるのか?(友人の例も参考に)」「そして、意外とかかる経費のリアル」**について、会社員の方の負担と比較しながら、詳しく正直にお伝えしたいと思います。始める前に知っておくべき「お金の現実」を知って、賢くスタートしましょう!
フードデリバリーって、ぶっちゃけどんな仕事?魅力と現実
フードデリバリーのお仕事は、お客様からの注文を受けて、飲食店で料理を受け取り、お客様のもとへお届けする、というシンプルなサービス業です。私たちは多くの場合、プラットフォームと業務委託契約を結び、個人事業主として働きます。
【魅力】
- 働く時間・場所が自由: 自分の都合に合わせて、好きな時間に、好きな場所で稼働できます。これは会社員にはない、最大の魅力でしょう。
- 煩わしい人間関係がない: 基本的に一人での作業です。上司や同僚との人間関係に悩むことはありません。
- 頑張った分だけ稼げる: 配達件数や距離、時間帯に応じて報酬が決まる成果報酬型です。たくさん配達すれば、その分収入が増えます。
- 比較的すぐに始めやすい: 車やバイク、自転車、スマートフォンがあれば、比較的簡単に登録して始められます。特別な資格は不要です。
【現実として知っておくべきこと】
- 収入が保証されているわけではない: オーダーがなければ収入はゼロです。天候や時間帯、エリアによって注文の入り方は大きく変動します。
- 経費は全て自己負担: 仕事にかかる経費は、全て自分で管理し、支払う必要があります。
- 体調管理・運行管理は全て自己責任: 体調が悪くても代わりはいません。安全な運行スケジュール管理も自分で行います。
- 事故のリスク: 交通事故のリスクはゼロではありません。安全運転はもちろん、万が一に備える必要があります。
- 確定申告が必要: 個人事業主として自分で収入と経費を計算し、税務署に申告する必要があります。
フードデリバリーの代表格!「Uber Eats」と「出前館」を知ろう
フードデリバリーのプラットフォームで代表的なのは、**「Uber Eats」と「出前館」**です。
- Uber Eats: 世界的に展開しており、多様な飲食店とユーザーが多いです。アプリの機能が充実しており、ピーク料金やクエストなどのインセンティブが頻繁に実施されます。
- 出前館: 日本発祥のサービスで、特に郊外など地域に密着した店舗網が強い傾向があります。独自のキャンペーンなどを実施することもあります。
どちらも、稼働したい日時を自分で決め、アプリで入る配達リクエストを受けるスタイルが基本です。
なぜ両方使うのが賢い?「ウーバー×出前館」組み合わせ戦略のメリット
フードデリバリーで効率よく稼いでいる多くのドライバーさんが実践しているのが、複数のプラットフォームを同時に、あるいは状況に応じて使い分ける戦略です。特にUber Eatsと出前館は、両方に登録して活用しているドライバーさんが多いです。これにはいくつかのメリットがあります。
- 注文機会の最大化: 一方のプラットフォームで注文が少なくても、もう一方から注文が入る可能性があります。待機時間を減らし、効率よく配達件数を増やすことができます。
- エリアや時間帯の得意不得意をカバー: プラットフォームによって、特定のエリアや時間帯に強い傾向があります。両方使うことで、様々な状況で注文を取りこぼしにくくなります。
- インセンティブの良い方を選べる: その時々で条件の良いプラットフォームの注文を優先したり、両方のインセンティブを見ながら戦略的に稼働したりできます。
- リスク分散: どちらか一方のプラットフォームでシステムトラブルやアカウントの問題が発生した場合でも、もう一方で稼働を続けられます。
複数のアプリ管理は少し慣れが必要ですが、効率的な稼働のためには非常に有効な戦略と言えます。
フードデリバリー、実際どれくらい稼げるの?リアルな収入事情
さて、収入についてです。友人の例で「年間売上450万円~500万円」という数字を挙げました。これは、週5~6日、1日8時間~10時間程度、積極的に稼働し、効率よく注文をこなした場合に達成可能な、目標となる売上金額です。
もちろん、これはあなたの活動エリア、稼働時間、車両(自転車かバイクか車か)、効率、そしてその時の注文需要によって大きく変動します。これから始める方が、すぐにこのレベルの売上を達成できるわけではありませんが、フードデリバリーという仕事には、これだけの売上を目指せる可能性があるということです。
稼いだ「売上」が、そのまま「手取り」になるわけじゃない!「経費」と「公的な負担」の真実
ここからが、フードデリバリーという働き方の、そしてどんな働き方にも共通する「お金の現実」です。
先ほどの年間売上450万円~500万円という金額は、あくまでプラットフォームから支払われた「売上(報酬額)」の合計であり、あなたが自由に使える**「手取り」ではありません!**
なぜなら、どんな働き方でも、稼いだお金から様々な「負担」が差し引かれたり、別途支払う必要があったりするからです。
1.フードデリバリー個人事業主の「経費」と「公的な負担」
フードデリバリーで売上を上げるためには、様々な経費がかかります。友人が言っていた**「年間経費150万円ぐらい」**というのは、フルタイムに近い稼働をしているドライバーとしては、現実的な金額と言えます。主な経費は以下の通りです。
- 車両関連費(多くを占める):
- 燃料費(ガソリン代/電気代)
- 車両購入費・リース料(減価償却費)
- 車検・点検・整備・修理費用
- タイヤ交換費用
- 車両保険料(任意保険)
- 駐車場代
- 装備品費:
- スマートフォン本体・修理代、モバイルバッテリー、スマホホルダー
- ヘルメット、雨具、業務用のウェアや靴(バイク・自転車の場合)
- 保温保冷バッグ(プラットフォーム支給以外)
- 通信費: スマートフォンのデータ通信費
- その他: 振込手数料など
売上からこれらの**「経費」を差し引いたものが、あなたの「所得」**となります。
そして、この所得に対して、以下の**「公的な負担」**が発生し、自分で計算して支払う必要があります。
- 税金:
- 所得税(国税)
- 住民税(地方税)
- 社会保険料:
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
友人の例(売上450万円~500万円、経費150万円)で考えると、
- 事業所得: 450万円 ~ 500万円 - 150万円 = 300万円 ~ 350万円
この所得に対して、あなたの扶養家族の状況などに応じて、所得税、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料が決まります。所得が300万円~350万円の場合、年間のこれらの公的な負担は、およそ60万円~100万円以上になる可能性もあります。(正確な金額は税務署や市区町村にご確認ください)
つまり、年間売上450万円~500万円の達成者でも、手取りとして自由に使える金額は、経費と税金・社会保険料を引いた残りの、年間200万円~300万円程度になる可能性がある、ということです。
2.会社員の場合の「経費的な負担」と「公的な負担」
では、会社員として働いている場合はどうでしょうか?会社員の方も、「額面給与」がそのまま手取りになるわけではありません。
- 給料からの自動的な差し引き(公的な負担): 会社員の給与明細を見ると分かりますが、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった税金や社会保険料が、給料から自動的に差し引かれています(源泉徴収)。特に社会保険料は、会社が半分を負担してくれますが、残り半分は給料から天引きされるため、手取り額が大きく減る要因となります。
- 仕事にかかる自己負担(経費的な負担): 会社員の方も、仕事をする上で様々な費用を自己負担しています。
- スーツ、ワイシャツ、革靴などの被服費
- 仕事で使うカバン
- 通勤にかかる交通費(全額支給されない場合)
- 仕事関連の書籍代や自己啓発費用
- 会社用の携帯電話がない場合の、自分のスマホの通信費の一部
- 同僚との飲み会などの交際費の一部
- (職種によるが)資格取得費用など
ただし、これらの自己負担費用は、原則として所得税の計算で給与所得から差し引くことはできません。 (特定支出控除という制度はありますが、利用できる人は限られます。)これは、フリーランスが事業に必要な経費を所得から全額差し引けるのと比較すると、大きな違いです。
【比較して分かること】
フードデリバリーの個人事業主は、**事業に必要な経費(車両費など)**を自分で管理し、売上から差し引いて所得を計算し、その所得に対して自分で税金や社会保険料を支払います。
一方、会社員は、給料から税金や社会保険料が自動的に差し引かれ、さらに**仕事に必要な費用を自己負担(所得から差し引けない)**しています。
どちらの働き方でも、「額面」または「売上」が、そのまま「手取り」になるわけではないという点は同じです。差し引かれる「負担」の内容や計算方法、支払い方が違うだけなのです。
フードデリバリーで年間売上450万円~500万円を達成している人が、年間150万円の経費を差し引くと所得が300万円~350万円程度になり、そこから税金・社会保険料がさらにかかる、という現実を理解しておくと、「売上が高くても、手取りはこういうイメージになるんだな」と、冷静にスタートできるでしょう。
これからフードデリバリーを始める人へ!成功のための第一歩
フードデリバリーの収入と経費のリアル、そして会社員との比較を通して、「思ったより経費や公的な負担があるんだな…」と感じた方もいるかもしれません。でも、これはどんな働き方でも共通する「お金の現実」です。適切な知識と準備があれば、フードデリバリーはあなたにとって強力な収入源となり得ます。
これからフードデリバリーを始めるあなたへ、成功のための第一歩を踏み出すためのアドバイスです。
- 情報収集をしっかり行う: 利用したいプラットフォームの登録要件、報酬体系、インセンティブ、活動したいエリアの需要などを調べましょう。公式サイトや説明会、経験者のブログやSNSなども参考にすると、よりリアルな情報が得られます。
- 必要な準備を万全に: 使用する車両(自転車、バイク、車)の確保はもちろん、安全のための装備(ヘルメット、プロテクターなど ※バイク・自転車の場合)、スマートフォン、スマホホルダー、モバイルバッテリー、配達用のバッグ(プラットフォームからレンタル/購入、または自分で用意)などを準備します。特に、万が一の事故に備えて、対人・対物賠償が無制限の任意保険には必ず加入しましょう! 業務で使う車両の場合、保険料は高めになることを想定しておきます。
- 複数プラットフォームへの登録を検討する: 可能であれば、Uber Eatsと出前館の両方、あるいは興味のある他のプラットフォームにも登録してみることをお勧めします。実際に稼働してみることで、ご自身の活動エリアや、稼働したい時間帯に、どのプラットフォームが強いのか、ご自身に合っているのかが分かります。最初から両方登録しておき、比較しながら慣れていくのが効率的です。
- 最初の目標設定は「安全」と「慣れること」に: 最初から高収入を目指しすぎると、無理な運転をしてしまったり、焦ってミスをしたりする可能性があります。最初のうちは、「安全運転で、配達の流れやアプリ操作に慣れること」「無理のない範囲で数件配達してみること」を目標にしましょう。経験を積むごとに、自然と効率は上がっていきます。
- 「経費管理」と「確定申告」の知識を学ぶ: 個人事業主として収入を得る以上、日々の経費を記録し、自分で確定申告を行う必要があります。経費を証明するためのレシートや領収書は必ず保管しましょう。最初は簡単なノートや表計算ソフトでも構いません。確定申告の時期に慌てないよう、基本的な知識を学んでおくことが大切です。
- 無理のない稼働時間からスタート: 体力や集中力に合わせて、1日2~3時間など、短い時間から始めてみるのが良いでしょう。慣れてきたら、徐々に稼働時間を増やしていくのがおすすめです。
まとめ:フードデリバリーは「リアル」を知って始めるのが成功の鍵!
フードデリバリーは、自分のライフスタイルに合わせて自由に働ける、魅力的なお仕事です。Uber Eatsや出前館といったプラットフォームを上手に活用し、戦略的に稼働すれば、年間売上450万円~500万円といったレベルも十分に可能であり、これは会社員の平均的な年収と比較しても遜色ない、あるいはそれ以上の金額となり得ます。
しかし、この売上は、車両関連費を中心に、年間150万円程度の経費がかかることで得られる売上であるという現実、そして、その所得から税金や社会保険料といった公的な負担が発生し、手取り額が決まる、という現実をしっかり理解しておくことが重要です。
これは、会社員が額面給与から自動的に税金や社会保険料が差し引かれ、さらに仕事にかかる費用を自己負担しているのと同じように、どんな働き方にも存在する「額面 ≠ 手取り」という現実なのです。
これからフードデリバリーを始めるあなたは、この「収入の可能性」と「経費の現実」、そして「複数プラットフォーム活用のメリット」を理解した上でスタートすることが、成功への鍵となります。適切な準備を行い、安全運転を心がけ、効率よく、そして経費管理もしっかり行うことで、フードデリバリーをあなたの強力な収入源として、長く続けていくことができるはずです。
この記事が、あなたのフードデリバリー挑戦の一歩を、現実的で確かなものにする助けとなれば幸いです。
さあ、準備ができたら、勇気を出して最初の配達に出てみましょう!あなたのチャレンジを応援しています!ご安全に!