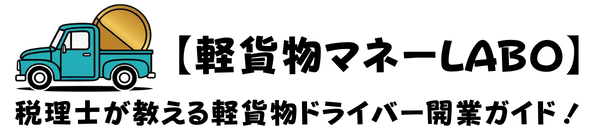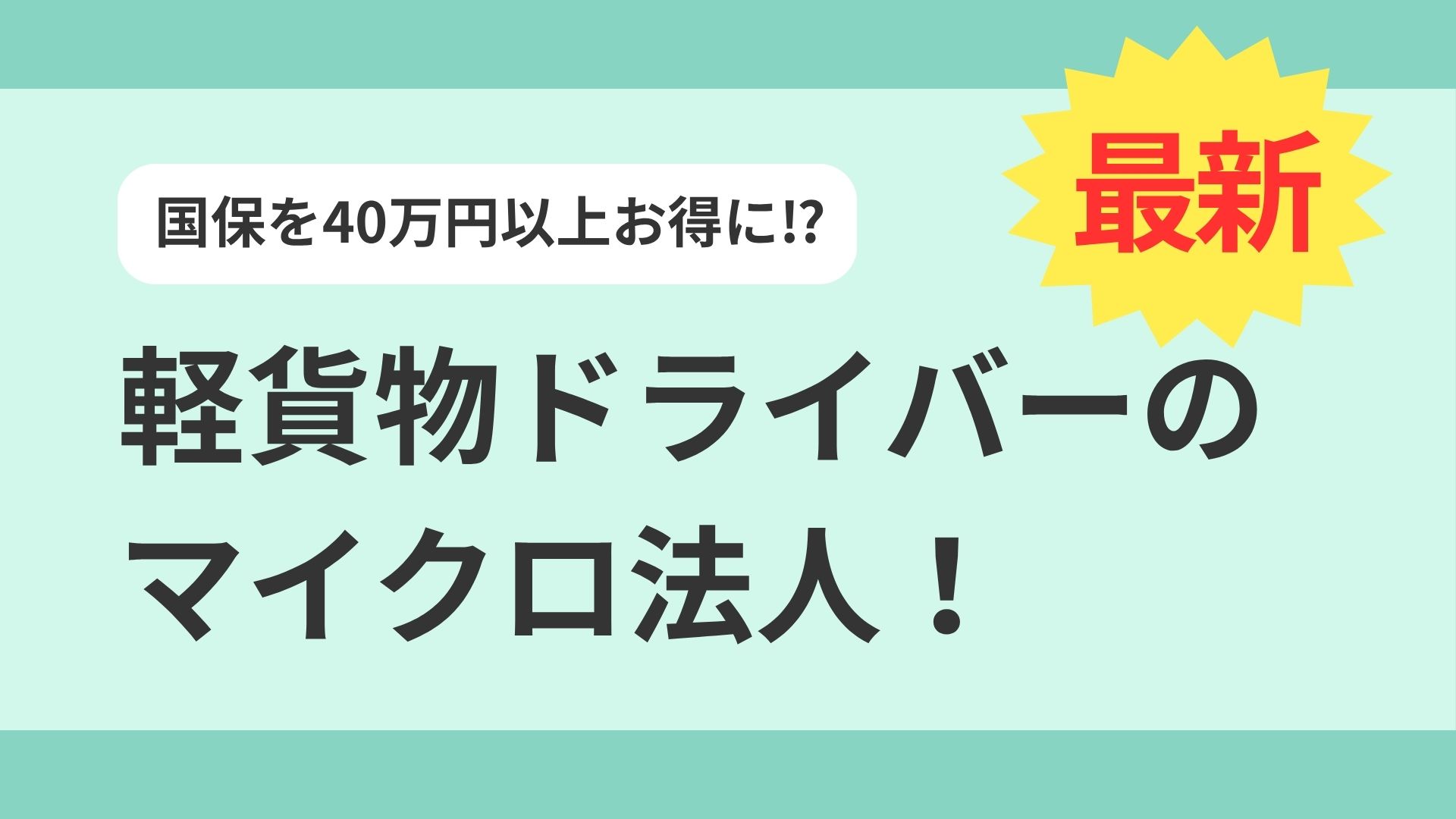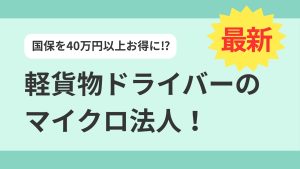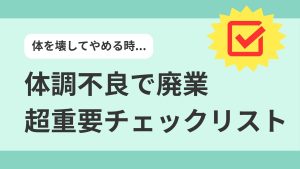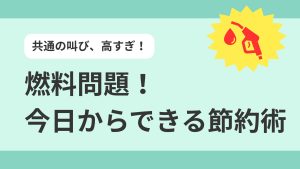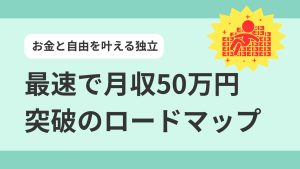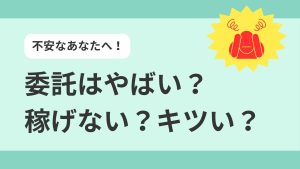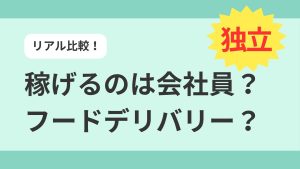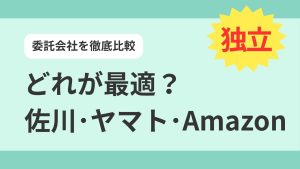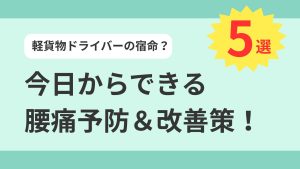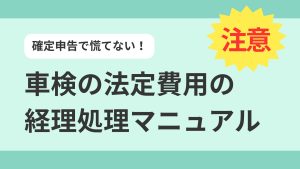軽貨物運送業を営む個人事業主の皆さん、日々の運転、本当にお疲れ様です!
事業が順調に進み、売上が上がってくると、大きな喜びを感じる一方で、税金や社会保険料の負担が増えてくることに頭を悩ませる方も多いでしょう。特に、私たち個人事業主の最大の悩みの一つが、一生懸命稼いだ利益から支払う**「国民健康保険料、なんでこんなに高いの!?」**ということではないでしょうか?
ご提示いただいたように、例えばあなたの年間所得がある程度の金額になった場合、国民健康保険料だけで年間40万円、国民年金保険料と合わせると年間60万円以上(国保40万円+国年20万円 ※ご提示の例)の負担になることも珍しくありません。この金額が、毎年の確定申告の時期などに「こんなに保険料を払うの!?」という形で目の前に現れると、本当に大きな負担に感じますよね。
そして、この「高すぎる国民健康保険料の負担を減らしたい」という切実な思いから、**「マイクロ法人」を作ると良いらしい、という話を耳にしたことがあるかもしれません。さらに、「国民健康保険の負担が年間40万円以上になってきたら、マイクロ法人設立のメリットが発生する」「個人事業の所得(利益)が年間300万円以上がマイクロ法人の検討ライン」**といった、具体的な目安を聞いて、より具体的に検討を始めた方もいるでしょう。
今回のブログでは、この「国民健康保険料の負担を減らしたい」という明確な目的を持つ軽貨物ドライバーさんに向けて、マイクロ法人とは何か、なぜ法人化が国民健康保険料の負担軽減に繋がる可能性があるのか、あなたがマイクロ法人を設立すべきか判断するための具体的な基準について、ご提示いただいた金額例や、社会保険料の仕組みに関する詳細な説明、そして失敗しない税理士選びのポイントも加えて、分かりやすく解説します!メリットだけでなく、デメリットや知っておくべきコストもしっかりお伝えしますので、あなたの事業にとって最適な選択をするための参考にしてください。
頑張って稼いだのに…「国民健康保険料」が重すぎる本当の理由(個人事業主の悩み)
まず、なぜ個人事業主の国民健康保険料が高くなってしまうのか、その理由を改めて確認しましょう。これは、私たちが個人事業主であることの**「国民健康保険料の計算方法」**に由来する悩みです。
国民健康保険料は、主に**前年の「事業所得」(売上から経費を引いた利益)に基づいて計算されます。所得が高ければ高いほど、健康保険料の金額も段階的に上がっていきます。これは、「所得割」**と呼ばれる、所得に一定の料率をかけて計算される部分があるためです。頑張って稼いで所得が増えるほど、この「所得割」の金額が大きくなり、国民健康保険料全体の金額が上昇していく仕組みなのです。
そして、個人事業主として事業で得た「利益(所得)」を、国民健康保険料の負担を減らす目的で意図的にコントロールする(少なく見せる)ことは、税法上の「脱税」に該当する可能性が極めて高い行為です。適正な売上と経費に基づいて計算された所得を申告する義務がありますから、国民健康保険料が高いからといって、所得を自由に操作することはできません。
つまり、個人事業主である限り、あなたの事業の「本当の利益(所得)」に対して、正直に、そして自動的に計算されて課せられる国民健康保険料の金額を、あなたの意思で「今年は安くしたいな」とコントロールすることは、仕組み上できないのです。これが、「国民健康保険料が高い…」という悩みの根本原因の一つです。ご提示いただいたように、年間所得が300万円を超えるあたりから、国民健康保険料が年間40万円といった金額になってくる(地域によって計算が異なるため目安です)など、負担を重く感じ始める方が多いのです。
救世主?!「マイクロ法人」とは?なぜ社会保険料を「コントロール」できるの?
そこで登場するのが、この「国民健康保険料の計算方法」の仕組みから合法的に最適化するための戦略として注目されている「マイクロ法人」です。
マイクロ法人とは、一般的に、個人事業主が、事業の一部または全部を切り離して、自分自身を役員(社長など)とする小さな会社(株式会社や合同会社など)を設立することを指します。そして、その法人は、役員であるあなたに「役員報酬(給料)」を支払います。
では、なぜマイクロ法人を作ると、社会保険料を「コントロール」して、負担を減らすことができる可能性があるのでしょうか?その仕組みを、ご提示いただいた構造も踏まえて説明します。
- 「個人事業」を同時運用しながら、副業的に「法人役員」への身分を持つ: あなたがマイクロ法人を設立し、その会社の社長になると、あなたの身分は「個人事業主」であると同時に、あなたが設立した「法人の社長」という扱いになります。
- 社会保険の切り替え: 個人事業主は「国民健康保険」と「国民年金」に加入しています。しかし、あなたが法人から役員報酬(給料)を受け取るようになると、その法人は**「健康保険」と「厚生年金保険」**への加入が義務付けられ、あなたもそちらの社会保険に加入することになります。(これにより、これまで加入していた国民健康保険と国民年金は脱退します。)
- 保険料の計算方法が変わる! ここが最大のポイントです。国民健康保険料は、あなたの**前年の「事業所得」に基づいて計算されます。一方、健康保険料・厚生年金保険料(合わせて「社会保険」と言います)は、法人から受け取る毎月の「役員報酬」(標準報酬月額)**に基づいて計算されます。
- 社会保険料は「役員報酬の金額に合わせて自動で設定される」: 健康保険料も厚生年金保険料も、毎月の役員報酬額が属する「標準報酬月額等級」という区分に基づいて、保険料額が自動的に決まります。 役員報酬額が高ければ保険料も高くなり、役員報酬額が低ければ保険料も低くなります。
- マイクロ法人なら「自分の役員報酬を自分で設定できる」: 個人事業主の所得は、事業の結果として決まるもので、意図的な操作は難しいです。しかし、マイクロ法人の役員であるあなたは、ご自身の役員報酬額を、原則として自由に(ただし、税務上の妥当性や事業の実態に合わせて)設定することができます。 (一度決めた役員報酬は、事業年度中は簡単に変更できないなどのルールはあります。)
- 社会保険料は「法人と折半」になる! あなたが支払う社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の負担は、個人(あなた自身)と法人(あなたが作った会社)で約半分ずつとなります。
この構造、つまり**「役員報酬額を自分で設定でき、社会保険料はその設定した役員報酬額に応じて決まる」という仕組みを利用することで、個人事業で得ていた高い「事業所得」に基づいて計算されていた国民健康保険料(全額自己負担)よりも、法人から受け取る低い「役員報酬」**に基づいて計算され、個人と法人の社会保険料の合計額の方が、結果として安くなる可能性が生まれるのです。
ご提示いただいた金額例で、大阪府の最低等級で社会保険(介護保険料あり)に加入した場合の個人の負担額を見ると、
- 社会保険(個人と法人の合計額):約8.5万円(年間)
- 厚生年金(個人と法人の合計額):約20万円(年間) 合計で、年間約28.5万円の社会保険料となります。(※これは、ご提示の金額を参考に、社会保険料の最低等級で計算した場合の目安であり、正確な金額はお住まいの地域や設定する役員報酬額で異なります。)
もし、国民健康保険料と国民年金保険料を合わせて年間60万円(国保40万円+国年20万円)支払っていたとすれば、マイクロ法人を活用することで、個人と法人の年間の合計負担額が約28.5万円になり、社会保険料の差額だけ見れば、年間約31.5万円の削減メリットがあることになります。
【ここが肝心】マイクロ法人設立が「お得になる」判断基準:社会保険料の削減 vs 法人維持コスト
マイクロ法人を設立すると社会保険料が安くなる可能性があることは分かりました。では、あなたの軽貨物事業でマイクロ法人を設立することが、経済的に「お得になる」のは、具体的にどのような状況なのでしょうか?判断基準は、シンプルに**「社会保険料の削減メリット」と「法人設立・維持にかかるコスト増」を天秤にかける**ことです。
1.社会保険料の削減メリットはどれくらいか?
ご提示の例(国民健康保険40万円、国民年金20万円 → マイクロ法人の社会保険、厚生年金 28.5万円)で考えると、社会保険料の年間削減メリットは、約31.5万円です。(これは、あくまでご提示の金額例に基づく計算です。)
2.法人設立と維持にかかるコスト増はどれくらいか?
これがマイクロ法人化による「デメリット(費用増)」となる部分であり、社会保険料の削減メリットと比較すべき金額です。ご提示いただいたコスト例を見てみましょう。
- 法人設立にかかる初期費用:
- ご提示なし。株式会社で約20万円~25万円、合同会社で約10万円程度が目安です。これは初年度のみにかかる費用です。
- 法人維持にかかる年間ランニングコスト:
- 法人住民税の均等割: ご提示の例:年間約7万円。(法人の所得がゼロでもかかる、年間定額の税金)
- 税理士費用: ご提示の例:年間約22万円。(法人の税務申告は複雑なため、税理士への依頼が必須級。顧問料+申告費用など)
- 合計年間ランニングコスト増(ご提示の例を合計): 約7万円 + 約22万円 = 年間約29万円
3.「社会保険料の削減メリット」>「法人設立・維持コスト増」となるか?
上記1で計算した「年間社会保険料削減メリット額:約31.5万円」と、上記2で計算した「年間法人維持にかかるランニングコスト増:約29万円」を比較します。
ご提示いただいた金額例に基づけば、
- 削減メリット額(約31.5万円) > ランニングコスト増(約29万円) となり、
- 年間 約2.5万円 の負担減少 となる計算になります。
4.所得レベルの目安:検討を始める「ライン」
社会保険料は所得が高いほど大きく増えるため、マイクロ法人設立による社会保険料削減メリットも、個人事業主としての所得が高くなるほど大きくなります。様々なシミュレーションや経験則、そしてご提示いただいた目安から、一般的には、個人事業主としての所得(税金・社会保険料を引く前の事業所得)が年間300万円以上、そしてそれに伴う国民健康保険料が年間40万円を超えてくるあたりが、マイクロ法人を設立することによる社会保険料削減メリットが、法人維持コストを上回り、「経済的にメリットが出る可能性が高まる」と言われている「検討を開始するライン」であると言えます。
ご提示いただいた金額例は、この「検討ライン」でのシミュレーション例として非常に参考になります。ご提示のコスト例では単純比較ではメリットが見えにくい結果ですが、これは税理士費用など、法人化による追加コストが具体的に含まれているためです。**年間国民健康保険料が40万円、または所得300万円以上というのは、「マイクロ法人を検討し始める具体的な目安」**として捉えるのが良いでしょう。
社会保険料だけじゃない?マイクロ法人設立のその他のメリット・デメリット
社会保険料の負担軽減が主な目的ですが、副業をマイクロ法人化することで、それ以外のメリット・デメリットも存在します。
その他のメリット:
- 役員報酬は法人目線では経費: 法人にとっては役員報酬は支払うべき経費になります。もし、副業収入を法人の法人の売上に計上されると、法人側の利益計算をする時に、更なる節税効果が発生します。
- 税金の種類を分散し、トータルで税負担が軽くなる可能性: 個人事業所得にかかる所得税だけでなく、法人税や給与所得控除なども活用できるため、全体として税金・社会保険料の負担が最適化され、軽くなる可能性があります。
- 経費にできる範囲が広がる可能性: 個人事業では経費として認められにくい費用でも、法人であれば親族への給料、福利厚生費、社宅家賃の一部、生命保険料(法人契約)など、経費として認められる範囲が広がり、課税対象となる所得を減らせる可能性があります。
- 対外的な信用: 法人の方が、個人事業主よりも社会的な信用度が高いとみなされる場合があります(例えば、銀行融資など)。
- 事業承継: 将来、事業を誰かに引き継ぐことを考えている場合、法人の方が手続きがスムーズな場合があります。
その他のデメリット:
- 経理・税務処理の複雑化: 法人の税務申告は、個人事業主の確定申告に比べて格段に複雑になります。税理士への依頼が必須級となる最大の理由であり、それに伴う費用が発生します。
- 設立・維持に手間がかかる: 法人設立手続きはもちろん、設立後も社会保険の手続き、税務申告手続き、役員変更登記など、手続きが増え、手間がかかります。
- お金が自由に使えない: 法人のお金と個人のお金は法律上明確に分けられます。法人の事業で得た利益を、個人が自由に引き出して使うことはできません。個人が法人の利益を使うには、マイクロ法人に詳しい税理士さんに相談することがオススメです。
- 限定責任は限定的?: 法人は出資した範囲で責任を負う「限定責任」が原則ですが、小規模な会社が事業用のローンを組む際などは、経営者個人が連帯保証を求められることが多く、実質的な責任が個人事業主と変わらない場面も多いです。
これらの要素を、経済的なメリット・デメリットと合わせて総合的に判断する必要があります。
【最終判断は専門家に!】失敗しない税理士選びと、あなたにとって最適なシミュレーション
マイクロ法人を設立すべきかどうかの判断は、あなたの現在の所得、家族構成、お住まいの地域(これにより国民健康保険料の計算方法が異なります)、今後の事業計画、そして法人化後の役員報酬設定や、依頼する税理士費用など、様々な要因が複雑に絡み合います。インターネット上の一般的な情報や、金額例だけでは、あなたにとって本当にメリットがあるのか、最適な判断をすることは非常に難しいです。
最も信頼できる、そして必ず相談すべき相手は、「マイクロ法人に詳しい税理士さん」です。
ご提示いただいたように、マイクロ法人に詳しい税理士さんに相談すると、役員報酬をいくらにすれば、社会保険料と税金全体で最も有利になるか、そして法人設立もどうやって進めればいいか?なども、あなたの状況に合わせて具体的に教えてくれるので安心です。
税理士さんを選ぶ際は、以下の点を考慮しましょう。
- マイクロ法人や個人事業主の法人化に詳しいか?: 法人化のメリット・デメリット、手続き、設立後の税務などに精通している専門家を選びましょう。
- 個人事業主側の事業(軽貨物運送業)を理解してくれるか?: 軽貨物運送業特有の経費などについても理解がある方が、スムーズなコミュニケーションや的確なアドバイスを期待できます。
- 個人事業主側の税金も合わせて総合的に相談できるか?: マイクロ法人化後も、あなたの個人事業(あるいは個人)としての確定申告は必要です。法人と個人の税金・社会保険全体を考慮したアドマルイスをしてくれる税理士さんを選びましょう。
- 料金体系が明確か?: 顧問料、記帳代行料、決算申告料など、かかる費用が明確か確認しましょう。
相談に行く際は、直近の確定申告書類の控え、国民健康保険料・国民年金保険料の通知書、そして大まかな年間売上と主な経費(特に車両費など)の金額を準備していくと、スムーズに具体的なシミュレーションをしてもらえます。
まとめ:マイクロ法人は「魔法」じゃない。あなたの状況で「お得」になるかを専門家と見極めることが重要。
国民健康保険料が高いと感じている軽貨物運送業の皆さんにとって、「マイクロ法人」は、その負担を軽減するための有効な手段となる可能性があります。特に、年間所得が300万円以上、そしてそれに伴い年間国民健康保険料が40万円を超えてくるあたりは、マイクロ法人化を検討を開始する具体的な目安となります。
マイクロ法人化により、所得に基づき上昇し続ける国民健康保険料から、役員報酬に基づき計算される社会保険へと切り替え、さらに保険料の約半分を法人が負担する形にできるため、社会保険料負担を軽減できる可能性があります。
しかし、マイクロ法人設立は、設立費用、法人住民税の均等割、社会保険料の法人負担分、そして税理士費用といった、これまでかからなかった新たなコストが発生することを意味します。これらのコスト増を、社会保険料の削減メリットや税金全体で見た場合のメリットが上回るかどうかを、正確に試算することが不可欠です。
マイクロ法人化による経済的なメリットがあるかどうか、そしてあなたにとって最適な選択であるかどうかは、あなた自身の具体的な所得や家族構成、お住まいの地域、そして設立後の役員報酬設定や依頼する専門家費用によって大きく異なります。 インターネット上の一般的な情報や金額例だけでは判断せず、必ずマイクロ法人に詳しい税理士さんに相談し、あなた自身の状況に基づいた正確なシミュレーションをしてもらい、メリットとデメリットをしっかり理解した上で、慎重に判断してください。
マイクロ法人は、所得が高くなってきた個人事業主にとって、社会保険料負担を最適化し、手取りを増やすための力強い味方となり得ます。ご自身の事業にとって最適な選択を行い、安心して日々の業務に取り組んでいきましょう。
皆さんの事業の、さらなる発展と、賢明な選択ができることを心から応援しています!
【この記事の監修は】

税理士 三浦研二 先生
元々は「売れない俳優・家電量販店の店員」でした。35歳で税理士登録をし、
心理学・DXに業務領域を展開中です。